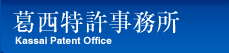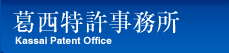|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
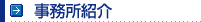

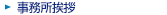

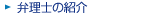

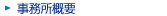

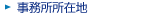
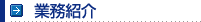







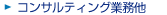






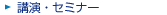



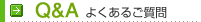
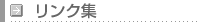
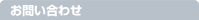 |
| 葛西特許事務所
|
〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
|
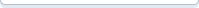 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|

【役立ち知識:商標】商標権侵害
(2015/01/15) |
| |
商標は、商品やサービスに付ける文字や図形などのマークから構成されますが、そうした商標について特許庁に商標登録出願を行い、審査によってその商標が所定の要件を満たしていると判断されると、一種の財産権である商標権が発生します。
ところで、登録された商標(以下、「登録商標」と言います)と同一又は類似する商標をその商標の権利者(以下、「商標権者」と言います)以外が勝手に使用していると、そのような行為は商標権の侵害となるのが原則です。
さて、商標権者が自らの登録商標と同一又は類似の商標を勝手に使用している第三者を発見した場合には、その者に対して商標権侵害である旨の警告書を送付することがあります。
警告書を受けた第三者としては、不意に警告を受けた時点で慌てふためいてしまうかもしれません。ですが警告書の内容が必ずしも正しいとも限りませんので、冷静に対処する必要があります。
そこで、以下では警告書を受けた場合には何をすべきかについて簡単にご説明致します。
1.回答期限について
警告書に回答期限が設定されているか確認します。ちなみに回答期限に法的意味はありませんが、相手方の心証を害さないためにも放置したままにしないでください。又、期限的に余裕がないときには、回答日を待ってもらえるよう相手方に求めておくと良いでしょう。
2.警告書で指摘されている内容の確認
相手方の商標権の内容の他、現に有効な商標権であるか、相手方が正当な権利を有しているか等を確認します。
3.指摘された製品や商標の確認
警告書で指摘された製品や商標を確認します。そして警告書の内容に応じて、例えばその商標の使用が相手方の商標権の侵害に当たるか否かを検討し、判断結果を相手方に回答します。
尚、こうした検討は容易ではないので専門家や特許庁に判断を依頼することをお勧めします(但し、これらの判断結果に法的効力はありませんのでご注意ください)。
4.その他
「商標権侵害かな」という直感が働いたら、製品を売り場から一旦引き上げる等の作業が必要な場合もあります。というのは、例えば後に商標権侵害の訴訟にまで発展したような場合、警告書を受けてもなおその登録商標を使用していると、そうした行為は故意であると判断されてしまい、不利になることがあるからです。又、相手方がその登録商標を使用していないような場合、相手方の商標権を消滅させる対抗手段もあります。
以上、警告書を受けた場合の対処例を簡単に述べましたが、警告書の内容によって対処も異なります。従って、警告書の内容は的確に把握することが肝心です。
尚、使用している商標がその登録商標に係る商標権の侵害に当たると判断されてしまいますと、商標権侵害であると知らずに使用していた商標を使えなくなるばかりか、その使用していた商標に蓄積されていた信用やブランド力まで失われてしまうことも考えられます。
よって、こうした事態に陥るのを未然に防ぐには、近い将来に使用予定のある商標だけではなく、今現在使用している商標についても商標登録出願をして登録を受けることで、その商標について商標権を確保しておくことが好ましいと考えられます。そうすれば、自らの権利に基づいて商標を安心して使用できますし、万一その権利を侵害する者がいれば、その者に対して侵害行為の差止めや損害賠償等を請求できるようになります。
|
<前へ | 一覧 |
次へ>
|

 |